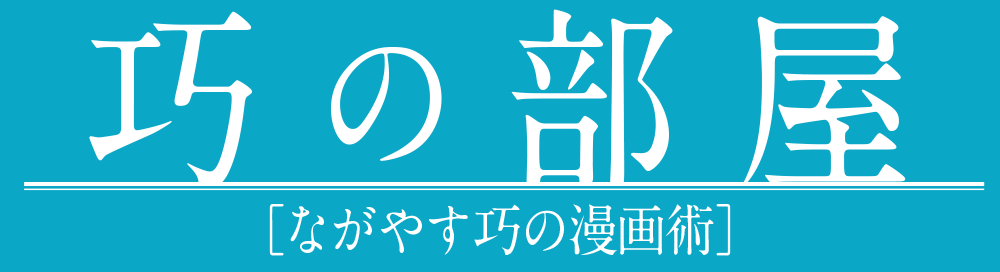
前回までに、ながやす先生のさまざまなコダワリや、漫画術をご紹介してきましたが、今回は、まだまだ残された秘密や、先生ご自身も「最後の最後にしか手をつけることのできない」聖域のページの話など、残された「ながやす巧流コダワリ」のあれこれをお話しましょう。
前回のラストでチラリとお話しましたが、『壬生義士伝』には、ながやす先生が各章執筆で「最後の最後に」、初めて手をつけるページがあります。
実はそれが、各章の扉ページです。
先生は各章ごとの原稿(およそ400ページ分)を全て描き終えた後、初めてこの「扉絵」に手をつけます。だから、各話の扉絵は本編作業が終わった後に、全部まとめて描くことになるわけです。
本編を全て描き終えた後だからこそ(物語の登場人物たちを昇華させた後の)一番いい表情が描ける…というコダワリなのでしょうか。
ともあれ「本編モード」が終了した後でないと「扉絵モード」に頭が切り替わらない…というコダワリは、まさに「ながやす流」!
先生がホワイト修正で使用するのは「ミスノン(正確にはミスノンW-20)」と「ドクターマーチン ペンホワイト」の2種類です。
「ミスノン」には刷毛がついていますし、「ドクターマーチン」のほうも、普通の漫画家さんのように筆につけて使用することもあるのですが、このほかに先生は直接、ペンの先に修正液をつけて原稿に「ホワイトでペン入れする」場合があります。
修正箇所の面積が小さい場合など、ペン先に(筆に取った修正液を)流しこんだり、あるいは(「ドクターマーチン」の場合は)容器の蓋についたスポイトを使ってペン先に流し込み、そのまま原稿にペン入れするというワケですね。
デジタルで原稿の修正処理を行う作家さんは別として、生原稿で筆を使わずにホワイトを入れる作家さんは…相当に珍しいのではないでしょうか?
ただ、この方法は「先生独自のコダワリ」というより、単に漫画家生活の「最初の頃から、こうやっていたから」習い性になったということらしいです。
ちなみに、以前はミスノンのような修正液ではなくポスターカラーでホワイトを入れていたそうですが、古い原稿などでは修正部分が乾いてひび割れ、ザラザラと落ちてしまうのだとか。
ある作品を単行本で再版するとき、昔の原稿の300ページ分まるまる、ホワイト部分が剥がれ落ちてしまい、修正するのに一月半かかったそうです!
スクリーントーンを基本処理した画稿の上にトーンを重ね貼りしたり、削り込みを入れたりするとき、先生はカッターナイフの刃(それも1枚の小さな切片だけ)を手に持って処理します!
あの小さな切れ端を親指、中指に挟んで、トーンを切ったり削ったりするわけですね。
普通、漫画家さんはカッターナイフを使う場合はホルダーから先端をチキチキと出して手に持ちますね(トーンナイフの場合にも切片はホルダーに刺して使います)。
…というか、こういうテクニックを使う作家さんは、相当に珍しいのでは?
いつ頃から、こんな方法を取っておられるのかは分かりませんが、ちなみに「トーンを削るテクニック」を体得されたのは、かの『愛と誠』連載の後期だそうです。
まあ、いずれにせよ相当に慣れていないと、間違えて刃の切っ先を指に刺してしまいそう。初心者やよい子は真似しないほうがよさそうです!
…というわけで「ながやす巧流コダワリ」のあれこれを御紹介し終えた後で、次回からはながやす巧先生と原作者浅田次郎先生、そして『壬生義士伝』との運命的な出会いに始まる打ち明け話のあれこれをお届けすることにしましょう。